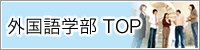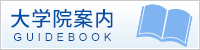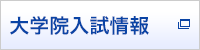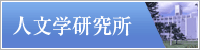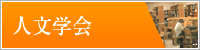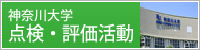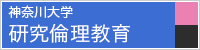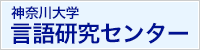Student life- 学生生活 -
大学院生の声
歴史を理解することは人間を理解することに繋がります。
学生生活について教えてください
私は中国・安徽省の南京の近くにある滁州出身です。「安徽中医薬大学」を卒業した後、上海社会科学院歴史研究所の大学院に通った後、一度、イギリス系の「GamesWorkshop」社に就職しましたが、知識の不足を痛感し、ちょうどコロナ禍のこともあり、仕事をすべて辞めて日本に来ました。そこからが大変で日本語の勉強や日本の生活になれるのが精一杯!でした。そのあと、神奈川大学大学院に入学はしたものの、次は研究テーマを決定することでさらに1年間、迷いました。いまは、中国を代表する開港都市の上海で近代的な養鶏業がどのように成長、発展したのか、を研究テーマに定めています。今までの人生は回り道だらけでしたが、現在は大学のサバゲーサークルに入り、TA活動にも従事するなどMMキャンパスの生活を満喫しています。
中国近現代史に関連する資料を集め、分析し、発表の準備を進めます。
コツコツと努力することが大事です。
授業の具体的な内容について教えてください。
大学院生の授業はゼミ形式の少人数です。私は中国近現代史専攻ですので、授業では清末から民国時期までの史資料を解読していくことが主な内容でした。取り上げる史資料は、中国側の史料もあれば日本側の史料もあります。これらの史資料から各自が興味のあるテーマを選び、関連する資料を集め、分析し、発表の準備を進めます。指導教授は資料の探し方や使い方を教えてくれたり、史資料の歴史背景の補充説明をしてくれます。また、研究テーマを掘り下げていく可能性や発展性などについてアドバイスをしてくれます。
私は院生のときに多くの講演会とシンポジウムにも参加しました。中には専攻に関わる中国の租界史や中国人留学生史に関する研究会もあれば、中国都市研究の国際シンポジウム(上海)など色々なものがありました。絵はがきコレクターのドナルド・ラップナウ氏の講演会やNHK国際放送局・中国語放送の仕事についての講演会にも参加するなど、多様な視点で日本と中国の関係を見ることができたと思います。
後輩に伝えたいことは?
地道にコツコツやること。大学院での勉強は、自らが取り組むことが前提です。自由に活用できる時間も多いです。しかし、2年という時間はあっと言う間に過ぎてしまいます。下手すると、何の結果も残さないまま無駄なってしまいます。だからこそ、コツコツと努力を積み上げることが大事です。何事に積極的に取り組み、挑戦しましょう。
今までの学生生活とは一味違う院生生活
授業の具体的な内容について教えてください。
私は現在人文学研究科の欧米言語文化専攻に在籍しており、スペイン語の条件文に関して言語史の側面から研究をしています。指導教員の元では、条件文、スペイン語史に関する授業、そして他の先生方からはそれに関連する言語学や歴史学の授業をしていただいております。指導教員の授業では、教材としてスペイン語で書かれた書籍や文献を使用するため、事前に自身で予習を行い、授業内でその内容の確認や解説をしていただくという形になっています。また定期的に研究の経過報告の発表を行っています。授業の内容自体も学生のレベルや研究内容に沿った形にしていただけるため、より自身の専門分野に精通することができ、一層知識を深めることが可能です。さらに授業外問わず手厚いサポートをしてくださり、非常に有意義な大学院生としての生活を過ごすことができています。
大学院生活について教えてください。
私は大学で先生方の授業の補助としてTA(ティーチングアシスタント)をさせていただいております。仕事内容としては、スペイン語学科の生徒の小テストや課題の確認や準備などを行っています。仕事の内容自体スペイン語に触れる機会が多いため、同時に自身のスペイン語力の向上にも繋がり、非常に有意義な時間を過ごすことができています。
研究活動にいたしましては、空き時間を利用し研究内容に関連する文献などを読んだり、まとめたりしています。基本的に英語かスペイン語で書かれおり、その上内容が難しくまだ読むのに時間を有してしまうため、空き時間にコツコツ読んでいくことを心がけています。
また7月頃にみなとみらいキャンパスにも人文学研究科の学生が利用できる研究室も作られ、より一層集中して研究に取り組むことが出来るようになりました。